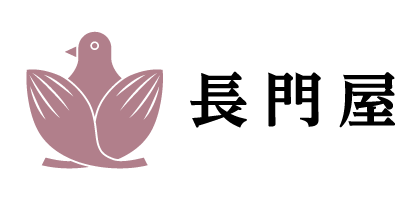その他
山形ビエンナーレ2022終了しました
2023.01.25
代表の笹林です。
長門屋も作品の展示場所のひとつとさせていただいた、東北芸術工科大学主催【山形ビエンナーレ2022】は、9/3からはじまり、終了いたしました。
4年ぶりのリアル開催となったビエンナーレ。長門屋の敷地奥のひなた蔵と塗蔵の2つの蔵も4年ぶりに展示会場となりました。それぞれで浅野友理子先生の作品展「草木往来」と、内藤正敏先生・草彅裕先生の写真展「二つの自然」を展示させていただいていました。
ひなた蔵に展示をされた浅野友理子さんは、4年間ご実家のある塩釜からひなた蔵に通って「長門屋の歴史」をヒアリングしてくださり、今回はその出会いから生まれた作品を展示されたので、私にとってとても感慨深かったです。
画家さんというものはご自身の強いインスピレーションによって作品を生み出すのだろうと思っていた私にとって、浅野さんの、出会った場の歴史や物語に興味を寄せ、それをいったん自分の体に取り込み咀嚼して、絵という形に変換させてこの世に生み出すあり方に、とても心動かされました。
たくさんの人を敷地の中に呼び込み、作品だけでなく、秋の花が咲き、虫が音を奏でる庭や陰影ある蔵という
建物の風情も一緒に、来る人の記憶に残したであろうビエンナーレ。
私自身も、週末ごとに若い学生さんやアーテイストさん等、普段は馴染み薄い分野の方々との出会いと会話を楽しませていただきました。
長門屋店舗で働くスタッフたちも、会期中はその様子をFBに上げたり、店から蔵への道案内係や蔵でお香を焚く香りのプロデュース係として、終了後は搬出お手伝い係として、陰ながら活躍しておりました。
私が浅野さんから直接、作品の説明をお聞きしたのは3週目の週末のことで、そのお陰で、これまで浅野さんと交わした会話と目の前の絵の関係性がわかり読み解きが進みました。
本当は来場される方全員に、読み解きの話をお伝えしたいくらいでした。

上の作品には、漆の木が描かれています。キャンバスの板は、長門屋のオリジナル「山形の桜の珠数」の材料として保管していた山形市内で育った太い桜の木を挽いたものです。
作品名は「はじまりの木」。
その理由を、浅野さんは以下のように紹介なさっていました。
もともと漆器店から始まった長門屋さんは、漆が取れる土地を探して、この土地にやってきたのだそうです。このひなた蔵にもたくさんの漆器や、縁あってたどりついた品々が保管されてきました。現在は人が集う場所として、お雛様の展示会や漆器のお膳を使用した食事会などが開かれています。訪れる度、蔵のしつらえや庭の変化から季節の移ろいを楽しませてくれます。
小さな桜の木々には長門屋さんにまつわるお話の中で印象深かった植物の姿を描いています。桜の木材の一部は、ひなた蔵の脇に数珠作り用に保管されていたものを譲っていただいたものです。作品には様々なものや行き交うこの場所を重ね合わせています。

上の作品は、同じく桜の板に、米沢藩に残された「かてもの」という本に記録された食べられる植物を描いたもの。よく見ると、フキノトウやトチノミなど見覚えのある植物が並んでいます。
浅野さんは、この上にガラス板を載せてテーブルにしてお茶を飲みたいとおっしゃいます。私もそんな機会があったらお呼ばれして、お茶にあずかりたいと妄想しております。
山形ビエンナーレの会期は13日間という短い期間でしたが、その実現のため、それまでにどれだけの時間が準備にかけられ、何人が繋がりあって動いてきたのでしょう。2年に1度、継続して開催されてきたことで、水面下で会期以外も休むことなく育ち続けているヒトやコトの広がりこそが、見えない財産となり次回を生み出していくのだろうと思いました。